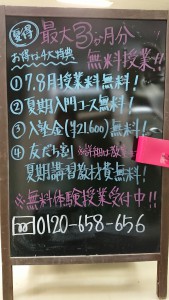心より願う
西日本豪雨で被害を受けた方々が、1日も早く笑顔になれる日を心より願っております。
また、この未曽有の大雨による災害で亡くなられた方々のご冥福を、心より祈っております。
本日より、進光ゼミナール西川田教室では、募金活動を始めました。
本当は、被災地に行き、被災された方々のために、何か行動をしなくてはいけない。
本当は物資を直接被災地に届けたい。
でも、今すぐにそれをすることは難しい。でも、少しでも被災地の皆様の役に立ちたい。
だから、生徒たちと考え、話し合い、今すぐにできる募金活動をし、
義援金として被災地のために送ろうということになりました。
こんなことしかできないけれど、今ここにいて、できることがあるのなら、まずはそこから始めよう。
がんばろう!西日本!
いつだって、私たちは皆様のために祈り、応援しています。
七夕
7月7日 七夕
教室でも小中学生を中心に短冊に願いを込めて笹(100均で購入!)に吊るし、七夕をお祝いしました。
今回は七夕の由来を簡単にご紹介いたします。
 七夕の由来
七夕の由来
七夕は「たなばと」と呼ぶのが一般的ですが「しちせき」と読むこともあります。その歴史は古く日本のお祭りの行事の中でもとても長い間大切にされてきました。
※五節句
人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)
七夕の由来とされている3つのもの
七夕の原型(由来)しているとされていると言われているものは3つ存在していて、それぞれが7月7日に深く関係のある物ばかりです。中には時代の流れとともに形をかえるなどして伝えられています。
①棚機(たなばた)
日本の神事として行われていた「棚機(たなばた)」というものがあります。読み方は七夕(たなばた)と同じものですが、その中身には違いがあります。
「棚機(たなばた)」というのは神事でつかう着物の織り機の名前で、古くから日本の行事「禊ぎ(みそぎ)行事」で乙女が着物を織る時に使われていました。
その際に織物を神様の祭ってある棚に供え秋の収穫の豊作を願ったり人々のけがれを払う為に行われていた神事です。
この「棚機(たなばた)」を使う事が出来るのは選ばれた乙女のみでそのときに選ばれた女性の事を「棚機女(たなばたつめ)」と呼びます。
選ばれた女性は機屋(はたや)にこもり神様にお供えする着物をおります。
そのご仏教の伝来にともなってこの行事はお盆の準備として7月7日に行われるよう日に変化し「棚機(たなばた)」と同じ読み方で七夕と当て字になったと言われています。
②おりひめとひこぼしの伝説
七夕の季節になるととても輝くふたつの星があります。その一つは琴座のベガと呼ばれる星は裁縫の仕事の星、鷲(わし)座のアルタイルといわれる牽牛(けんぎゅう)星は農業の仕事の象徴の星として古代中国で考えられてきました。
この2つの星の間には天の川と呼ばれるように小さく輝く星が無数に輝く川の両側に存在しています。
この2つの星は旧暦の7月7日頃(現在の8月7日頃)に一番輝きを見せることから
2つの星がお互いを求めているように見える事をもとに七夕ストーリーが作られたと言われています。
③乞巧奠(きこうでん)という織物への願い
中国の行事に乞巧奠(きこうでん)というものがあります。琴座のベガと呼ばれる星は裁縫の仕事の星ということもあり、古く中国では織女星にあやかって織物の上達などをお祈りする風習が生まれました。
今では7月7日は織物だけではなく芸事や書道などの上達をお祈りする日として続いているようです。
平安時代に日本に伝わってきた七夕の行事
古くの日本には七夕という文化はなく伝わってきたのは平安時代の頃と言われています。
日本に伝わった当初は宮中行事といて七夕行事が行われていました。当時の宮中行事のなかでとても重要視されていたのは作物を育てる時期や季節の変化を民に伝えるというものがあり、それらは様々な物を用いて行われていました。
そのため星座をもとにされる七夕の行事はとても重宝されていたようです。
七夕の頃には宮中の人々は桃や梨、なす、うり、大豆、干し鯛、アワビなどを供えて星をながめ、香をたいて、楽を奏で、詩歌を楽しみました。
短冊の元になる物もこの頃に誕生し、里芋の葉にたまった夜露を「天の川のしずく」と考えそのしずくで墨を溶き、古くから神木として考えられていた梶(かじ)の葉に和歌をしるし願い事をしていました。
江戸時代の頃から七夕行事は一般の人も楽しむようになった
一般の人が七夕を楽しむようになったのは江戸時代のころからです。この頃に七夕が五節句にとりこまれ一般庶民に広まりお祝いをしていました。七夕が一般に広がった当初、人々の願い事の多くは詩歌や習い事の上達などを願い事にしていたようで、野菜や果物をおそなえして願い事をしていました。 梶の葉は神木として大事にされていた事もあり、この頃から今見る事が出来るような五色の紙に願い事を書くようになっていったようです。
現在の七夕
7月7日はおりひめとひこぼしが1年に1度だけ会う事が出来る大切な日、2人が会いたいという願いが叶う日という事も合って、2人のように願い事が叶いますようにと短冊に様々な願い事を書いて笹に吊るすという行事になりました。
笹や竹が使われるのは冬でも緑色を失う事なく生命力の強い植物で不思議な力がある植物として扱われてきました。
竹取物語などをみてもそこに不思議な生命力が授けられていると昔の人が感じ取っていたことが分かります。七夕の時に使用した笹や竹は川や海に飾りごと流すというのはけがれをいっしょに流すという意味も込められているようです。
私たちの身の回りにある伝統的な行事には、古くからの言い伝え、慣習、智慧などさまざまな想いが込められているものです。
その想いを正しく伝えていくことが私たち大人の使命ではないかな?なんて最近になってようやく考えられるようになりました。
今まで何も感じずに生きてきましたが、日本て本当に素敵なところがいっぱいある魅力的な国だと思います。
私たちが見過ごしている日本の素晴らしさも生徒たちに伝えていきたいと思います。
中間テストを終えて
今週、西川田教室に通塾している中学生全員が、今年度初の定期テスト「中間テスト」を終えました。
中学1年生にとっては、中学校に入学し、初めての本格的なテストでした。
塾では、6月1日から、毎回の授業後に小テスト(計算30問、英単語15問)解きなおしに取り組み、
6月9日、6月16日には、学校別に模擬テスト、理社暗記会を行い、中間テストに備えてきました。
はたしてみんな、努力してきた成果を十分に発揮できたであろうか?
テスト終了後には、テスト問題を回収し、解きなおしを行います。
テストで大切なことは、しっかり準備をすること、そして、テストが終わったら
そのまま放置するのではなく、解きなおしをし、その日に出来なかった問題を復習し、
解き方をマスターして、今のテストのときの自分よりもさらにレベルアップしましょう!
テストで結果を出すということも大切なことですが、
それよりも大切なことは、テストを通じて自分のできないところを通じて、
「できない」ことを「できる」ことに変え、自分自身を成長させていくことです。
テストの結果に満足するだけではなく、さらなる成長を目指し、テストを活用しましょう!
理社暗記会のお知らせ!
前期中間テストに向けて、理社暗記会を行います!
6月16日(土)
16:00~17:40 数学・英語 中間テスト模擬テスト
18:00~20:00 理科・社会 暗記会
*16:00からは、はじめて中学校の定期テストを受ける中学1年生のために、
中間テストの過去問を使い、中間テストを模擬体験してもらいます。
小学校のテストとは違い、テスト範囲は広く、問題数も多くなります。
事前に体験することで、テスト中の時間の使い方や、テストまでの勉強の仕方も変わります。
最初のテストだからこそ、良い準備をして、やり残しのないようにしよう!
理社暗記会は、理科社会の重要事項をひたすら暗記する気の遠くなるようなイベントです!(笑)
覚えるまで帰れないとても有意義な一日をプレゼントします!
*理社暗記会は、保護者には大人気ですが、生徒は厳しい顔をするイベントです!(笑)
理科実験教室
みなさんこんにちは!
大変遅くなりましたが、先日(5月19日)に行った、
理科実験教室のご報告です!
今回の理科実験教室は、洗濯のりと食塩を使ってスーパーボールを作る実験です。
昨年までは、スライム(洗濯のり+水+ホウ砂→スライム)を作ったのですが、
今回は、スーパーボールにチャレンジしました。
どのような実験かというと、
洗濯のりに食塩水を入れて混ぜると白い塊がでてきます。
その塊を取り出して 形を整え、水分がなくなるまで手で丸めると、スーパーボールのように弾む物体ができるというものです。
簡単に原理を紹介すると、
洗濯のりには、PVA(=ポリビニルアルコール)というプラスチックの一種がたくさん水に溶けています。
そこに食塩を混ぜると(食塩はとても水に溶けやすい物質です)、食塩に水分を取られたPVAの
プラスチックが溶けきれなくなり、固体となって出てきたものがスーパーボールです。
この現象を「塩析(えんせき)」といいます。
今回の実験では、最初は食塩水を使って実験を行いましたが、
あまり固まらず、水分が抜けるまでに相当な時間がかかったため、
最後は、食塩をそのまま洗濯のりに入れてみたところ、
食塩を直接入れたほうが、固まりも早く、よりスーパーボールに近いものが出来上がりました。
みなさんも、夏休みの自由研究などで取り組んでみてはいかがでしょうか。
材料もほぼすべてドラッグストアなどで入手できます。
理科の知識は、私たちの身の回りにたくさん活用されており、
理科実験室以外でも簡単にできる実験がたくさんあります。
こういった身近な道具を使った実験から、生徒たちが理科に興味を持ち、
学問への探求心が芽生えるような、知的好奇心を刺激するような実験を
お届けしたいと思います。