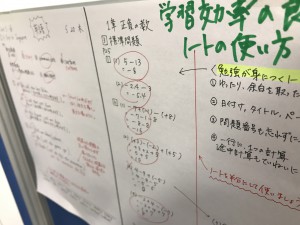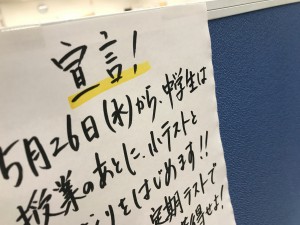私の注意の仕方
西川田教室の新井です。授業中も休み時間も、生徒同士または生徒と講師の間に笑い声や指導する声が絶えず聞こえる賑やかな教室の日々は、暑い夏に負けないほどの活気と熱意があります。8月も猛暑が続くと思われますので、教室の熱気に負けないように水分補給を忘れず、勉学に取り組んでもらえればと思います。
生徒自身も教室全体も活気があるのは良いことです。しかし賑やかすぎてしまったり、学習から大きく脱線してしまったりすると、塾としての本来の役割を果たすことができません。そんな時に私は修正すべく注意をしますが、その注意の仕方で心がけていることが1つあります。
それは、「私の気持ちをそのまま伝える」ことです。
例えば、生徒が何かいけない行動を取ったとき
「あなたがそのようなことをするのはだめなことだからやめなさい」と言ってしまうと
間違った行動がその子だけの問題になってしまいます。そうではなく
「あなたがそのようなことをすると、私や周りのみんなが困るからやめてほしいな」と伝えることで
間違った行動がその子だけでなく、周りの人たちを含めた問題になっているのだと捉えてもらうことができます。
この手法は教育心理学でも、指導の際に扱うべきものとして挙げられる内容の一つです。
その子自身のために行動を改めるよう促すよりも、その子と仲の良い相手や周りの人たちのために行動を改めるよう促す方が、改善するよう動くことが多いという実験結果が出ています。
ですから、私は注意を促す際に、自分がその行動を取られてどう思っているか、周りにどんな影響を与えているか伝えるようにしています。
そのためにも生徒をしっかりと見て、その生徒に合った声掛けを徹底したいと思っています。