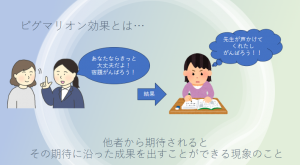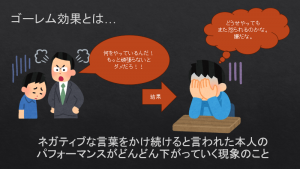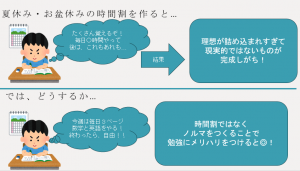頑張るキミの味方でありたい!
こんにちは、鶴田北教室の菊池です。
十月になりました。本格的な秋のシーズン到来ですね。
スポーツの秋、芸術の秋、読書の秋などと言われているように、
様々なことに取り組みやすい時期です。
また、味覚の秋であることも忘れてはいけませんね。
生徒達には、美味しいものをたくさん食べて、
元気に学校生活を過ごしてほしいと思っています。
さて、本日は、「涙が出るくらい嬉しかったこと」について書きたいと思います。
小学生のA君は、掛け算の九九が苦手でした。
一から五の段までは正確にできる一方、六の段以降になると、
間違えたり、手が止まったりしてしまいます。
そこで、鶴田北教室では、A君に毎回、九九の計算問題を用意し、
夏期講習中も、毎回練習してもらいました。
時には、授業中、講師の先生と一緒に音読もしました。
そして、先月の中旬、A君に九九の計算プリントを渡し、
計算してもらったところ、見事全問正解していました。
採点をしていて、涙が出そうになりました。
「この答案、お母さんに見せてあげてね」とA君に伝えました。
さらに、A君の親指を見ると、絆創膏が貼られていました。
「どうしたの?」と聞くと、
家で九九を音読しながら、お母さんのお手伝いをしていた時、
不注意で切ってしまったと話してくれました。
それを聞いて、「そこまでやらせてしまい、申し訳ない」という思いと同時に、
A君は時間を惜しんで練習していたことを知り、
またまた涙が出そうになりました。
A君からすると、この数か月は同じ問題を反復させられ、本当に辛かったと思います。
それでも、休まず授業に出席し、宿題も忘れずに提出してくれました。
「努力は裏切らないこと」をA君の姿から実感させられました。
鶴田北教室では、苦手克服に取り組む生徒が多くいます。
「頑張るキミの味方でありたい!」をモットーに、
生徒たちの最高のパートナーとなれるよう、日々頑張っていきます!