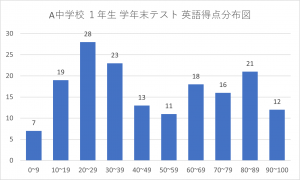理科実験教室を終えて
皆さんこんにちは。
進光ゼミナール西川田教室の岩崎です。
先日、5/20(土)に理科実験教室「水中エレベーターを作ろう」を行いました。
この「水中エレベーターを作ろう」は、浮沈子という容器を押したり、離したりすることで、中にあるものが浮いたり沈んだりする、圧力と浮力の関係を利用したおもちゃです。この実験は、浮力と圧力のバランスが重要で、実験を始めてすぐは、重すぎて沈んでしまったり、浮力が強すぎて、浮きっぱなしになってしまったり、いろいろな失敗がありました(一人だけ、とてもあっさりと理想的な浮沈子を作り上げた子もいました)。それぞれの失敗から、何が原因なのか考え、改善を行いました。もちろん、簡単に成功はしませんでしたが、何度も試行錯誤し、ついには、全員が成功をしました。一度、コツをつかむと、子どもたちは、私たち大人がサポートしなくても、何度も挑戦し、あっさりと私が作ったサンプルよりも、上手に作れるようになりました。子どもたちは自分が興味を持ち、「自分で作ることができた!」という成功体験を積むことで、あっという間に成長していく様子を見て、とても嬉しく、笑顔になれる時間を過ごさせもらいました。
参加してくれたみんな、本当にありがとう。
ちなみに、私がこっそりと実験していた「沈まない水」(ダイラタンシー)は、うまくできず失敗に終わりました。それでも、子どもたちは、興味を示し、楽しんでくれたようで「次は、あの実験(ダイラタンシー)しよう」と言ってくれました。
成功も失敗も、どちらの結果も起こりえるのが実験、それを心から楽しめる子どもたちのために、次回こそはダイラタンシーの実験を成功させたいと思います。