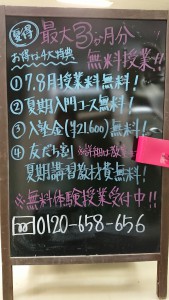夏期講習テキストを眺めながら
いよいよ7月23日より進光ゼミナールの夏期講習がはじまります。
今日は、教室に届いた夏期テキストを生徒一人一人に仕分けをしながら、中身を確認していきました。
テキストを仕分けしながら、「この生徒は、この問題には苦戦するだろうな」とか、
「この生徒は、次の期末テストまでに、こういった問題をできるようにしよう」とか、
いろいろと想いを巡らせ仕分けをしていたら、いつの間にか深夜になっていました!笑
いつも、授業が終わるたびに、「ほんとうにこの授業で生徒がしっかりと理解できたであろうか?」と自問自答します。
そして、決まって答えは、「もっと、○○すればよかったかな?」など、反省ばかりが浮かびます。
教育にゴールはないのかもしれませんが、
少しでも、今日の自分より成長して、子どもたちの成長の役に立ちたいと思いつつ、
そこよりも熱夏期講習になるように、夏期講習の用意をしています。